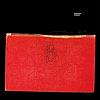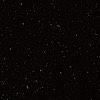長いこと熱心な音楽リスナーとして生きてきたがいまだにわかりそうでよくわからないのがジャズだ。
たとえば、なんらかの洋画を観ているときにBGMとしてジャズが流れてきたりして、
「お! いいなあ~ジャズ」
なんて思うことがわりとよくある。
で、昔中古で買ったマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンなどの有名どころのジャズミュージシャンのCDを引っ張り出してきて聴いてみるのだが、
「うーむ。……やっぱりわからん!」
となるのがお決まりのパターンである。
ただ、前述したとおりジャズはよくわからないが「ジャズっぽい曲」は私の大好物である。「ジャズっぽい曲」とは、ようするに、ポップス系のミュージシャンによるジャズのテイストが入っている楽曲のことである。
「本格的なジャズ」と違うのは私のようなジャズ音痴の人間にもひじょうにわかりやすいということだ。ジャズマニアの人からしたら鼻で笑われてしまうかもしれないが、「ジャズな気分」を味わいたいときにこれらの曲をよく聴いている。誰の参考になるのか知らないが、以下にいくつか挙げてみた。
Radiohead「You And Whose Army?」
陰鬱で美しいメロディ、ムーディな音色を響かせるギター&ベース&ドラムの演奏からなる「ジャズっぽい匂い」が色濃く漂っている曲だ。しかもポップで聴きやすいのがとてもいい。
この曲をジャズと言ったらジャズマニアの人に怒られてしまうかもしれないが、私にとってはアダルトかつ「ウィスキー。ロックで」的な雰囲気を味わえる「ジャズっぽい」名曲である。
Jamie cullum「Gran Torino」
この曲はクリント・イーストウッド監督・主演作の『グラン・トリノ』を観ていたらエンディングで流れてきて知った。
ジェイミー・カラムはウィキペディアに「ジャズ・シンガー」ときっぱりと書かれており、なので、この曲もジャンルで括った場合、ジャズとして解釈すべき曲なのだろうが、ジャズという音楽からどうしてもイメージしてしまう小難しさは一切なく、むしろとてもキャッチーでピアノバラード的なポップスとしての親しみやすさに溢れている。
Fiona Apple「Slow Like Honey」
こちらはフィオナ・アップルのファーストアルバム『Tidal』に収録されている。
優雅なピアノの旋律、しっとりと歌い上げるフィオナ・アップルの歌声が印象的であり、かつ、どこか気怠げな雰囲気を終始一貫として醸していて、艶っぽくてムーディでジャズっぽくもある曲である。
この曲をディナーショーで生で聴ける機会があったら是が非でも馳せ参じたいばかりだ。
小島麻由美「ハードバップ」
小島麻由美はデビュー時からジャズを積極的に取り入れているミュージシャンだ。こちらはそんな彼女の「ハードバップ」という曲であるが、そもそもジャズのひとつのスタイルとして「ハード・バップ」というものがあることはさすがに私でも知っている。
以下、ウィキペディアに掲載されている「ハード・バップ」の説明文を一部引用してみよう。
ハード・バップは(Hard bop) は、モダン・ジャズの一つ。アメリカ東海岸で、1950年代半ばをピークに1960年代まで続いたスタイル。
(中略)ビバップのように、コード進行に乗せた、あるいは、コード分解によるアドリブといった基本は一緒だが、それよりも、特にソロのアドリブ演奏面で、ホットでハードドライビングしながらも、メロディアスに洗練されたスタイルといわれている。また、よりフレーズが重要視されるため、メロディーとして成立しない音を音階からはずさざるをえないため、同じコードを使用しても、使えない音が出てくることが多く、ビバップよりも、融通性のないメロディーやフレーズとなりがちであった。
また、ハード・バップはアフロ・キューバン/ラテン音楽の要素、とりわけルンバやマンボ等を取り入れて、ラテン・ジャズへと発展していく。特にハード・バップで演奏されるものはアフロ・キューバン・ジャズといわれることが多い。
(Wikipedia-「ハード・バップ」-)
うん。
なにを言ってるんだかさっぱりわからん。
わからんが、少なくとも小島麻由美の「ハードバップ」を楽しむうえではとくにわからなくても問題ないのでどうだっていい。
小島麻由美の妖艶なヴォーカル、塚本功の粘っこくって、かつ、ソリッドでもあるギター、熱っぽさとクールネスが同居するリズムセクションでもって構築されているサウンドスケープは圧巻の一言に尽きる。ジャズっぽい「夜」のイメージを喚起させられるとともに、ポップスとしてのわかりやすさも兼ね揃えている名曲である。
Scoobie Do「A Chant For Bu」
「やたらとかっこいい曲だなあ」
と思ってあとで調べてみたら、ジャズドラマーとして知られるアート・ブレイキー、彼が率いるバンド「アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ」の曲のカバーバージョンであると知った。
クールかつグルーヴィなスクービーの演奏とホットなホーンセクションが気分を高めてくれること請け合いのナンバーである。
UA「波動」
UAのジャズ作といえばUA×菊池成孔の『cure jazz reunion』というアルバムも持っているが、個人的にはこちらの曲が収録されているライブアルバム『la』の方が断然好きだ。
もともとはUAがかつて浅井健一らと組んだロックバンド、AJICOの曲としてリリースされたものだが、こちらのライブバージョンはアンビエントな質感のあるサウンドで構築されているオリジナルバージョンとは大きく異なっていて、もう、どうしょうもなくジャズである(ように聴こえる)。厳密に言えばジャズとは言えないかもしれないが、きわめて「ジャズっぽい」曲だ。
それというのは、なにしろ日本の代表的なジャズミュージシャンたちがUAのバックを固めているからで、「ジャズな感じ」に仕上がっているのも当たりまえの話だ。
パワフルなUAのヴォーカルも、大人の色気たっぷりな鈴木正人のウッドベースも、腕が5本ぐらい生えてるんじゃないかと思えてしまうほど天衣無縫に暴れまわる外山明のドラムスも、なにもかもが素晴らしい。中でもこの曲の最大の聴きどころは菊池成孔の3分20秒あたりからはじまるテナーサックスのソロ演奏である。宇宙を切り裂くようなスリリングな吹きっぷりが最高に素晴らしい。
宇多田ヒカル「Hymne a l'amour~愛のアンセム~」
フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフの「愛の讃歌」のカバー。
海外ではもちろん、日本のシンガーでも越路吹雪、美空ひばり、玉置浩二など錚錚たるメンツがカバーしている曲であるが、宇多田ヒカルのカバーはかなり大胆と言えるだろうジャジーなサウンドに仕上げられている。
とにかく、エレピも、ベースも、ドラムも、所々で聴こえてくるフルートも、天にも昇ってしまうぐらい優雅で心地よい。心なしか宇多田ヒカルの歌声もいつもにも増して色っぽく聴こえて、これがまたよい。
以上である。
ジャズはよくわからないが、とりあえずこれらの「ジャズっぽい曲」を聴いて、日々お茶を濁している私である。
いつか
「ここのマイルスのアドリブ、超サイコーだよね!」
などとドヤ顔で語れるような日ははたして私の人生にやってくるのであろうか。
うん。たぶん無理だ。